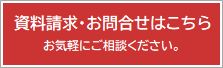こんにちは。伊與田塾 塾長の いよだです。
マインドアクセラレータの授業では、教材の一部としてボードゲームを利用しています。
今日のブログでは、「なぜボードゲームを教材として利用しているか。」について書きたいと思います。

まず大前提として、伊與田塾は国語算数などのいわゆる「教科の授業」はしていません。
伊與田塾は「将来役に立つ本物のかしこさをきたえる」ための授業をしています。
その上で、社会に出てから必要となるさまざまな能力を鍛えるためにボードゲームを採用しています。
さまざまな思考技術をきたえるため
ボードゲームといっても非常に多くの種類があり、それぞれ頭の使い方も多様です。言い換えると、たくさんのボードゲームをプレイすることによって、さまざまな思考法や思考技術を体験することができるのです。
伊與田塾では独自の思考技術の分類があります。以下に思考技術の大分類を挙げてみます。
論理力、空間認識能力、コミュニケーション力、語彙力、読解力、水平思考・・・
成長するための”態度の学力”を育むため
人生100年時代、将来にわたって成長をし続けるためには、成長するための「態度の学力」というものがあると考えています。ボードゲームは、態度の学力を伸ばすのに一役買います。
態度の学力の一部を紹介します。
能動性
自分以外の外部からの刺激によって受け身的に考える・行動するのは「受動的」と言えます。そうではなく、自分からゲームの盤面や他者へ働きかけられる能動性を身につけられます。ボードゲームではプレイ中に能動的に動かなければ勝てません。そして、あくまでゲームなので失敗のダメージが少ないことが大きいです。学校やリアルの人間関係の中での失敗はダメージが大きくなることもあり、大きな失敗はその後の能動性を萎縮させてしまう可能性があります。ボードゲームは学びの機会となる失敗を低リスクでたくさん経験できるものだと考えることもできるのです。

協力迷路探索「マジックメイズ」
論理性
自分の行動・アクションを理由や根拠に基づいたものにすることができます。勝利への筋道を考える。他者の行動を予測する。そのためには大なり小なりの論理に基づいて考える必要があります。

チェス+心理戦「ガイスター」
視野の広さ
マインドアクセラレータ初心者(ボードゲーム初心者)ほど、ゲームの盤面や状況が見えていません。どうしても自分の状況しか見られなかったり、独善的に行動してしまったりします。そうではなく、盤面全体、そして参加するプレイヤー全体に注意をいきわたらせる視野の広さをきたえることができます。

交渉がカギ「カタン」
教材として利用するときの留意点
注意が必要なのは、ただボードゲームを遊んでいるだけでは能力が伸びるとは限らないということです。
生徒の力を伸ばす授業として成立させるために、ボードゲームそのもの以外にも準備や仕掛けが必要ですし、講師による雰囲気作りや適切な声掛けなども必要になります。(そのあたりはまた、別の記事として書きたいですね!)